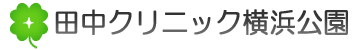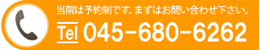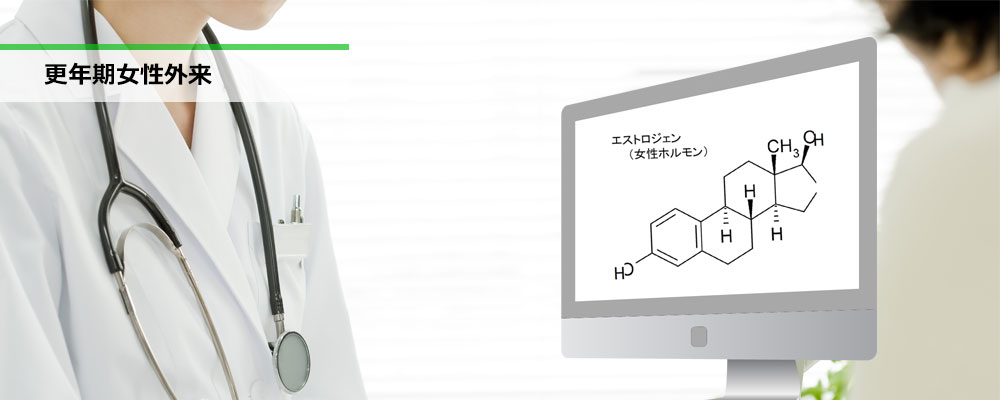ご挨拶

院長 田中冨久子
閉経後の女性たちへの女性ホルモン(エストロジェン)の補充という医療を
続けて、本年は14年目になります。昨年のご挨拶で申し上げましたように、本診療所では、40歳の後半から、いわゆる50歳代を中心とした更年期をすぎ、60歳代、時に80歳代の女性たちへのエストロジェンの補充も、その投与量、投与方法、などを変えつつ行なっております。そして、私の診療所のある医療圏では、60歳以降の女性たちへのこういった投与も、「卵巣機能欠落症状」への対応として「保険適応」が認められているからこそであることは昨年のご挨拶で書かせていただきました。
こうした広範囲にわたる年齢層の女性への女性ホルモンの補充は、私に取って大変興味のある事実を知らせてくれています。
つまり、50歳を中心とした更年期では、大方の女性において、その主な症状はホットフラッシュや発汗、うつ、不眠なのですが、それ以降では、個々の女性で、その訴える症状に個性があり、それに対する女性ホルモンの効果に個性があることに気がつきました。そのうちのいくつかの例をお話しして、更年期を過ぎた方々でも、こんな症状がなんとかならないか、などと訴えてくださると、私の意欲を増してくれると思いますので、どうぞよろしくお願いします。
例えば、1)80歳代の女性が、体が冷えて、冷えて、湯たんぽを抱えて寝る、と訴えてこられました。そこで、あるエストロジェンとプロジェステロンの配合剤を、通常は毎日という処方を3日毎に飲むように処方しました。その結果、すっかり、体が温まって、湯たんぽが不要になったということでした。
例えば、2)足が冷えて困ると訴えてこられた、やはり80歳代の女性には、例1)の女性を思い出し、しかし、この女性は筋腫のため子宮摘除を受けていましたので、エストロジェンの錠剤を2日、あるいは3日毎にして飲むように処方しました。すると、この女性では、足の冷えに対しては、まあまあの効果のようでしたが、おしゃれに長く伸ばしている髪の毛の抜け毛がめっきりと減少し、これが本当に嬉しいと感激しています。
例えば、3)60歳代で、日本画を趣味に描いている女性が、手における関節障害、つまりへパーデン結節とプシャール結節、それに手根管症候群を加えて患い、うまく筆を掴んで絵が描けないと訴えてきました。その方には、50歳代の女性へのエストロジェンとプロジェステロン量の半量の補充をしたところ、手が柔らかくなって絵が描けるようになったと喜ばれています。
例えば、4)いわゆる更年期にうつ症状を訴えて来院した女性において、通常のホルモン補充によってすっかり元気を回復した60歳前半に補充を中止したところ、関節リウマチを発症してしまいました。女性ホルモンがリウマチの発症を抑制するという説を確認することになったと思っています。
例えば、5)ある80歳代の女性の手の動きを眺めていた時、強い変形があることに気づき、尋ねたたところ、数年前に関節リウマチを発症して治療中とのこと。痛いのよ、との嘆きに対して、試しにと先のエストロジェンとプロジェステロンの配合剤を3日おきに、と処方しました。すると、痛みがすっかり取れた、と喜ばれています。乳がんや子宮がんについては、彼女は毎年大病院の人間ドックに入っているらしいので安心しています。
例えば、6)精神科で統合失調症と誤診され、投薬されてしまっていた50歳代の女性が母親に連れられて受診されました。女性ホルモン補充によって、すっかり健全な女性として働いています。
本年も、皆さんにとって良い年となりますように祈念いたします。
田中クリニック横浜公園について
田中クリニック横浜公園の更年期女性外来では、ホルモン補充療法を更年期障害とその後の障害の根本療法ととらえて治療を行うとともに、漢方薬による治療、生活習慣の改善の指導などによる治療を行います。
男性医師にはなかなか相談しにくい・恥ずかしいなどで悩んでいる方、女性特有の症状を配慮し、女性医師が更年期診療を行います。
また、毎週木曜日には更年期男性外来も行っており「LOH症候群診療ガイドライン」に従って男性ホルモン補充療法など、症状に応じた診療を行っております。
糖尿病、脂質異常、高血圧などを中心とした生活習慣病(メタボリック症候群)や、風邪・頭痛・腹痛などの急性疾患に対する診療と共に、何科に行けばいいのか分からないなどのご相談にも応じます。
必要がある場合は、症状に応じて、最適な専門医療機関をご紹介させて頂きます。
更年期障害とは?
女性は生まれてから子ども時代を経て、思春期といわれる12歳前後で初めての月経(初経)を迎えます。その後、周期的な排卵と月経が30数年間、続きますが、40歳代後半から無排卵性の不規則な月経周期となり、50歳前後になると月経が永久に停止します(閉経)。閉経年齢は平均50歳で、一般に、閉経をはさんだ前後10年間(40歳代後半から50歳代前半)は更年期と呼ばれています。
更年期には、それまで卵巣で合成・分泌されていた卵巣ホルモンの分泌が減少し、ついには全く欠落する現象がおこります。卵巣ホルモンは女性ホルモンと一般に言われますが、卵胞ホルモンであるエストロジェン、とくに17ベーターエストラジオール(E2)※1と、黄体ホルモンであるプロジェステロン※2があります。エストロジェンの血液中の濃度が低下すると、①のぼせ、ほてり、発汗などの自律神経失調症状、②イライラ、抑うつ、不安などの精神的症状、そして、③手のこわばり、関節痛などの運動器症状、④性交痛、頻尿などの泌尿生殖器症状などなどを自覚するようになります。これらを更年期症状と言います。そして、これらの自覚症状をもたらす原因は、エストロジェン欠乏によって体と脳に起こっている病的な障害で、更年期障害と呼ばれます。
更年期症状は、女性の日常生活を、大変つらい、過酷なものにします。また、たとえ更年期症状を乗り越えたとしても、多くの場合は、さらに卵巣機能欠落症状として続きます。そして、更年期障害として始まった体と脳の病的な障害は、生涯、進行します。
※1 参考サイト 17ベーターエストラジオール(E2)厚生科学研究「畜産食品中残留ホルモンのヒト健康に及ぼす影響に関する研究」
※2 参考サイト プロジェステロン 札幌臨床検査センター
診療方針
初診時に「問診票」と「SMI」という更年期のチェックシートを用い、症状の有無を確認します。更年期の症状は、卵巣ホルモン、特にエストロジェンの減少が背景にあることから、血液検査によって、E2の血中濃度とその分泌を支配する下垂体前葉ホルモンである卵胞刺激ホルモンFSHの血中濃度の動向を調べます。
また、更年期の症状は、甲状腺機能異常によるものとの鑑別が必要なため、甲状腺ホルモンであるT3とT4、加えて下垂体前葉ホルモンである甲状腺刺激ホルモンTSHの血中濃度も調べます。
さらに、脂質代謝の異常の有無を血中コレステロール/中性脂肪の測定により、糖代謝の異常の有無を血糖値、HbA1Cの測定により確認するとともに、骨密度や動脈硬化度を調べ、治療の方針を決めていきます。
なお、田中クリニック横浜公園では治療としてホルモン補充療法と漢方薬のどちらを選ぶかは患者様のお考えにしたがいますが、もし、ホルモン補充療法を選択される場合は、近年、ステロイドホルモン投与による血栓症のリスクが指摘されてきていますので、あらかじめ血栓に関する検査をさせていただき、治療中も定期的な検査を行います。